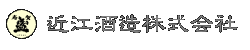(知りたい質問の箇所をクリックして下さい。)
営業日・営業時間は?
・営業時間は、原則として平日の9:00〜17:00。
平日でも、特に午後は外出等で事務所を空けている場合があります。来社ご希望の場合は必ず事前にご連絡お願いします。(連絡がない場合は対応いたしません…防犯と的確な対応のためにご協力お願いします。)
・土・日・祝日、お盆、年末年始はお休みをいただいております。
平日でも、特に午後は外出等で事務所を空けている場合があります。来社ご希望の場合は必ず事前にご連絡お願いします。(連絡がない場合は対応いたしません…防犯と的確な対応のためにご協力お願いします。)
・土・日・祝日、お盆、年末年始はお休みをいただいております。
蔵に来たら、小売をしているのですか?
小売販売は行っておりません。
通信販売はしているのですか? 遠方ですが商品をわけてほしい。
通信販売は行っておりません。かつて通信販売を行っていたサイトも閉鎖しております。当社にお電話を頂いても対応いたしかねます。
お酒の賞味期限・保存方法は?
基本的に日本酒は腐敗するものではないのですが、「温度×時間」でお味はどんどん変化していきます。
高温なところや日の当たるところでは特に変化が進みますので、暗く涼しい場所で保管して下さい。
弊社では開栓前1年以内に飲んでいただくことを目安としております。
開封後は、なるべく冷蔵庫で保管していただき1ヶ月以内にお飲み下さい。
長期間置いておき、「熟成酒」として楽しむ事もできます。酒質が変化したとしても、腐敗することはありません。お試しになられては如何でしょうか?
ただし、お酒が全体的に濁っていたり、濁っていないはずのお酒ににごりや沈殿物がある場合は、悪い方に変質している可能性がありますので、お飲みにならないことをおすすめします。(火落ちの可能性があるからです。)
商品の製造年月や賞味期限が書いていない。どういうことか。
製造年月について
清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示8号)が改正され、令和5年(2023年)1月1日以後に酒類の製造場から移出等される清酒について、製造時期の表示が任意記載事項になりました。
そのため、弊社では法令が改正された2023年1月1日以降に製造された商品については、具体的な日付を表示せず出荷しております。
なお、弊社の商品については、商品の品質を吟味した上で出荷しており、また出荷事績は当社で記録しております。
賞味期限について
消費期限や賞味期限は、食品や飲料であれば食品表示法によって記載が義務づけられているものですが、日本酒を含む酒類は、アルコール飲料である特性から長期間の保存に耐え得るものであるとされ、期限の表示を省略できることになっています。
ただし、酒類は保存状況や年数に応じて品質が変化してまいります。
当社では製造後未開栓状態で1年以内を目安にしておりますが、この期間を過ぎていたとしても飲むことに差し支えはありませんし、健康上の問題も考えられません。ただ、味わいは変化します。特に清酒の品質は、製造時期よりもむしろ保存方法等(酸素、温度、光等)に左右されます。清酒は、高温や急激な温度変化、日光や蛍光灯などの光にはよくない影響を与えるので、光の当たらない涼しい場所で保管するとよいでしょう。
但し、開栓済の場合は冷蔵庫など冷暗所に保存の上早めにお飲み下さい。味わいの変化や熟成がより早く進むからです。
蔵見学、社内見学は出来ますか?
社内の見学はお断りしております。酒蔵もありません。ご了承ください。
近江酒造への交通手段は?
・JR「近江八幡」又は「米原」「彦根」の各駅から近江鉄道へ乗り換え
・近江鉄道「八日市」駅下車、徒歩15分。
・近江鉄道バス、ちょこっとバス「西友前」または「大通り商店街東口」下車徒歩約2分。
・名神高速道路「八日市」インターチェンジより、421号線へ左折、「東本町」交差点を右折、「緑町」交差点角
近江酒造の事務所は、「緑町」交差点角の緑の屋根の建物の裏側の銀色の階段を上った所にあります。
・近江鉄道「八日市」駅下車、徒歩15分。
・近江鉄道バス、ちょこっとバス「西友前」または「大通り商店街東口」下車徒歩約2分。
・名神高速道路「八日市」インターチェンジより、421号線へ左折、「東本町」交差点を右折、「緑町」交差点角
近江酒造の事務所は、「緑町」交差点角の緑の屋根の建物の裏側の銀色の階段を上った所にあります。
駐車場はありますか?
あります。建物の前のスペースに止めて下さい。
なお、アパートやマンションの駐車場はその住民のための契約駐車場です。近隣の店の駐車場もその来店者のためのものです。トラブルの原因になりますので停めないようにお願いします。
迷ったらご連絡下さい。
なお、アパートやマンションの駐車場はその住民のための契約駐車場です。近隣の店の駐車場もその来店者のためのものです。トラブルの原因になりますので停めないようにお願いします。
迷ったらご連絡下さい。
社長が猫好きと聞いたのですが、猫さんには会えますか?
近江酒造の事務所では猫を飼っていません。悪しからずご了承下さい。
なお、社長宅ではペットの猫を室内飼いしています。
なお、社長宅ではペットの猫を室内飼いしています。
日本酒のラベルを収集している者です。ラベルを恵贈していただけませんか?
ラベルについては処分いたしましたので、お渡しできるほどの量は用意しておりません。あしからずご了承下さい。
敷地内にある機関車は見学できるのか
遠くから見学することは可能です。ただし、周辺は新築建物の工事をしておりますので、その際に工事車両の出入りや作業の妨げにならないように。また、周辺は交通量がそれなりにありますので交通の妨げや事故にあわないよう十分御注意下さい。
イベントの開催にあわせて、機関車の周辺にスペースを設けて、見学できるようにする予定です。
イベントの開催にあわせて、機関車の周辺にスペースを設けて、見学できるようにする予定です。
なぜ近江酒造は酒造業を休業する判断をしたのか?
一番大きな理由として、
酒造用機器や建屋が老朽化、故障が頻発しており、衛生に対する基準が厳しくなる中、高品質で安心安全な酒造りのためには莫大な費用を伴う修繕や設備投資が継続的に必須でありながら、その費用が捻出できなくなったことがあります。
その他、
・市街地に立地していることや少量生産による、高コスト体質。
・原材料費が急激に上昇しており、回復の見込みがないこと。それにも関わらず、商品の価格転嫁ができず収支を圧迫していること。→このことから、従前から厳しい経営を強いられてきました。
・少子高齢化の急速な進展により酒類とりわけ日本酒の需要のさらなる低下が予想されること。
・さらなる市場縮小の一方で、高度化かつ変化する顧客の嗜好に応えるためにさらなる設備投資、人材育成などが必要であるが、その資金が捻出できないこと。
などを総合的に判断いたしました
酒造用機器や建屋が老朽化、故障が頻発しており、衛生に対する基準が厳しくなる中、高品質で安心安全な酒造りのためには莫大な費用を伴う修繕や設備投資が継続的に必須でありながら、その費用が捻出できなくなったことがあります。
その他、
・市街地に立地していることや少量生産による、高コスト体質。
・原材料費が急激に上昇しており、回復の見込みがないこと。それにも関わらず、商品の価格転嫁ができず収支を圧迫していること。→このことから、従前から厳しい経営を強いられてきました。
・少子高齢化の急速な進展により酒類とりわけ日本酒の需要のさらなる低下が予想されること。
・さらなる市場縮小の一方で、高度化かつ変化する顧客の嗜好に応えるためにさらなる設備投資、人材育成などが必要であるが、その資金が捻出できないこと。
などを総合的に判断いたしました
蔵が壊されるときいたが、いつ、どうなるのか
2023年秋頃から年末にかけて蔵を解体しました。その後、土地を造成し、住宅会社に売却後、住宅地(分譲宅地、アパート)に生まれ変わりつつあります。
なお、2023年11月に弊社事務所を近隣地に移転いたしました。
なお、2023年11月に弊社事務所を近隣地に移転いたしました。
蔵が壊されたら敷地内にある機関車はどうなるのか
敷地内にある機関車はそのまま存置いたします。イベントや見学できるようにスペースを設けます。
これまでのブランドはどうなるのか
酒造業を行っていた当時の商品は、出荷を終了いたしました。
ただし、今後、別のメーカーが当社の商品ブランドを引き継いで製造販売することはあるかもしれません。
近江ねこ正宗については、長野県の株式会社舞姫様より、「信州ねこ正宗」という商品を出しておりますので、興味のある方はお試しいただければ幸いです。(近江ねこ正宗とは別のシリーズです)
なお、「志賀盛」「近江路」「近江龍門」「近江ねこ正宗」の商標権、インターネットドメイン名の権利は現在も当社が所有しています。
ただし、今後、別のメーカーが当社の商品ブランドを引き継いで製造販売することはあるかもしれません。
近江ねこ正宗については、長野県の株式会社舞姫様より、「信州ねこ正宗」という商品を出しておりますので、興味のある方はお試しいただければ幸いです。(近江ねこ正宗とは別のシリーズです)
なお、「志賀盛」「近江路」「近江龍門」「近江ねこ正宗」の商標権、インターネットドメイン名の権利は現在も当社が所有しています。
近江酒造はこれからどうなるのか
法人(会社)についてはそのまま存続しており、近隣地にて営業しております。事業としては所有不動産の賃貸に事業を集中して営業しています。
商号の変更は予定しておりません。
酒造免許は税務署に返納しました。販売免許は引き続き所持しております(まだごく少数の取引先に限り酒の販売は続けております)。
酒造業からは撤退いたしましたが、弊社として今後どのような事業展開があるかわかりませんので、あらゆる可能性を見据えて、敢えて今回は酒造業の「休業」と表現させていただきました。
今後ともどのような形でお世話になるかも知れませんが、その際はまたよろしくお願いいたします。
商号の変更は予定しておりません。
酒造免許は税務署に返納しました。販売免許は引き続き所持しております(まだごく少数の取引先に限り酒の販売は続けております)。
酒造業からは撤退いたしましたが、弊社として今後どのような事業展開があるかわかりませんので、あらゆる可能性を見据えて、敢えて今回は酒造業の「休業」と表現させていただきました。
今後ともどのような形でお世話になるかも知れませんが、その際はまたよろしくお願いいたします。
新たに酒造業をやりたいので、酒造免許を譲渡してもらえないか
弊社が所持していた酒類製造免許(酒造免許)については、2024年3月をもって、税務署に返納のうえ取消をうけました。したがって、当社から酒造免許を譲渡することはできません(譲渡しようにも免許がありません)。なお、事業譲渡やM&Aなどのお申し出が時々ありますが、以前からこのようなお申し出についてはお断りしております。
(ちなみに…)
酒造免許の譲渡については、免許のみ譲渡というのは認められず、法人の合併、買収(株式の譲渡取得)、相続しかないのが当局の方針となっています。
また、新たな免許付与についても、酒税法第十条の法令解釈通達によると、次の場合に限られます。
イ 清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
ロ 2以上の清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して清酒を共同製造しようとする場合
ハ 清酒製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
ニ 共同してびん詰めすることを目的として設立された清酒製造者が主となって組織する法人の蔵置場又は自己のびん詰等のための蔵置場に未納税移入した清酒に、炭酸ガス又は炭酸水を加え、発泡性を持たせた清酒を製造しようとする場合
ホ 輸出するために清酒を製造しようとする場合
(国税庁HPより)
それは、日本酒の全体的な消費量が減少(1973年をピークにして2024年ではその約1/4!)している中、新たな免許を多数交付するとなると、過当競争となり、既存の酒蔵の経営が圧迫、淘汰がすすみ、酒の出荷量の減少につながり、ひいては国税収入の重要な位置を占める酒税収入が減少してしまうことにつながるとされているからです。
もし、自らでお酒を造りたいのであれば、当然に免許は必須ですが、次の方法も検討できるかと思います。
・M&Aにより酒蔵(酒造会社、個人)ごと買収して経営を引き継ぐなら免許取得は可能で、新しい蔵つくることも可能でしょう。
・輸出用商品に限って製造できる輸出限定免許の形なら新規免許取得は可能です(前述)。
・委託醸造、つまり酒造免許を保有している他の酒蔵に製造してもらい、自社ブランドの日本酒を造ってもらう(OEM)、あるいはその製造過程に自ら参画するという方法もあるかも知れません。
・清酒以外の免許で清酒以外の酒類(リキュール、雑酒、クラフトサケ等)を造るという方法も考えられます。
いずれにせよ、いろんな可能性を柔軟に考えてみるのは如何でしょうか。
そのためにも、酒類製造免許の件について詳しいことは、お近くの税務署の酒類指導官部門に相談されるのが一番良いと思いますし、後々のトラブルが少ないかと思います。今後の税務署とのおつきあいも円滑に進むかも知れません(とても大事です)。
(ちなみに…)
酒造免許の譲渡については、免許のみ譲渡というのは認められず、法人の合併、買収(株式の譲渡取得)、相続しかないのが当局の方針となっています。
また、新たな免許付与についても、酒税法第十条の法令解釈通達によると、次の場合に限られます。
イ 清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
ロ 2以上の清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して清酒を共同製造しようとする場合
ハ 清酒製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
ニ 共同してびん詰めすることを目的として設立された清酒製造者が主となって組織する法人の蔵置場又は自己のびん詰等のための蔵置場に未納税移入した清酒に、炭酸ガス又は炭酸水を加え、発泡性を持たせた清酒を製造しようとする場合
ホ 輸出するために清酒を製造しようとする場合
(国税庁HPより)
それは、日本酒の全体的な消費量が減少(1973年をピークにして2024年ではその約1/4!)している中、新たな免許を多数交付するとなると、過当競争となり、既存の酒蔵の経営が圧迫、淘汰がすすみ、酒の出荷量の減少につながり、ひいては国税収入の重要な位置を占める酒税収入が減少してしまうことにつながるとされているからです。
もし、自らでお酒を造りたいのであれば、当然に免許は必須ですが、次の方法も検討できるかと思います。
・M&Aにより酒蔵(酒造会社、個人)ごと買収して経営を引き継ぐなら免許取得は可能で、新しい蔵つくることも可能でしょう。
・輸出用商品に限って製造できる輸出限定免許の形なら新規免許取得は可能です(前述)。
・委託醸造、つまり酒造免許を保有している他の酒蔵に製造してもらい、自社ブランドの日本酒を造ってもらう(OEM)、あるいはその製造過程に自ら参画するという方法もあるかも知れません。
・清酒以外の免許で清酒以外の酒類(リキュール、雑酒、クラフトサケ等)を造るという方法も考えられます。
いずれにせよ、いろんな可能性を柔軟に考えてみるのは如何でしょうか。
そのためにも、酒類製造免許の件について詳しいことは、お近くの税務署の酒類指導官部門に相談されるのが一番良いと思いますし、後々のトラブルが少ないかと思います。今後の税務署とのおつきあいも円滑に進むかも知れません(とても大事です)。
びわこジャズ(びわこジャズフェスティバル)の会場にはもうならないのですか?
2009年の第一回開催時から2023年開催時までの毎回、弊社の酒蔵敷地内をびわこジャズの会場の一つとして開催され、あわせて弊社の酒蔵開きを開催して、多くの方にお越し頂きました。毎回楽しみにされる方も多く、その際には大変ありがとうございました。
しかしながら、弊社の都合で酒造業に幕を下ろすこととなり、会場は再開発されることになり、これ以降は会場から外れることとなりました。現在、酒蔵の敷地は住宅地として再開発されつつありますが、その一部は機関車ED-314の静態展示場としてのスペースとして残しております。すでに、このスペースでは、例えば2024年秋のガチャフェスの会場の一つとしてイベントを開催してお客様をお招きしたこともあります。
びわこジャズ実行委員会によりますと、2025年開催分については、2024年秋時点ですでにびわこジャズの実行委員会で会場を内定しており、機関車の展示スペースを使用するプランは入っていないとのことです。
ただ、2026年開催時には検討して頂けるとの回答を得ています。必ずしも確約されたわけではありませんが、もしこの会場で開催してほしいという声があれば、是非びわこジャズ実行委員会に要望を上げて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
しかしながら、弊社の都合で酒造業に幕を下ろすこととなり、会場は再開発されることになり、これ以降は会場から外れることとなりました。現在、酒蔵の敷地は住宅地として再開発されつつありますが、その一部は機関車ED-314の静態展示場としてのスペースとして残しております。すでに、このスペースでは、例えば2024年秋のガチャフェスの会場の一つとしてイベントを開催してお客様をお招きしたこともあります。
びわこジャズ実行委員会によりますと、2025年開催分については、2024年秋時点ですでにびわこジャズの実行委員会で会場を内定しており、機関車の展示スペースを使用するプランは入っていないとのことです。
ただ、2026年開催時には検討して頂けるとの回答を得ています。必ずしも確約されたわけではありませんが、もしこの会場で開催してほしいという声があれば、是非びわこジャズ実行委員会に要望を上げて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
過去の活動や歴史、今後の方針等について問い合わせや取材は受け付けていますか?
弊社では現在、直接のお問い合わせや取材はお受けしておりません。過去の情報、今後の情報については、このサイトでお知らせするようにいたします。
求めているQ&Aが無かった。直接問い合わせたい。
近江酒造へのお問い合わせは >>コチラ